管理人のエビスです。
まとめノート(サブノート)を作る必要があるのかお悩みの受験生も多いのではないでしょうか?
結論から言いますと「まとめノート(サブノート)は作らない」です。
私自身、まとめノートを作ったことはありませんし、その必要性も感じたことがありません。
この記事では、まとめノート作りが不要な3つの理由と、その代わりにするべきことを解説しています。
行政書士試験に短期一発合格した現役行政書士が、勉強のコツを伝授します。
まとめノート(サブノート)を作らない3つの理由
まとめノートを作らない3つの理由はいかのとおりです。
・費用対効果が低い
・現在のテキストはすでにまとめられているので、さらにまとめる必要はない
・情報はテキスト1冊にまとめるべき
費用対効果が低い
受験生の中にはカラフルなペンを使って芸術的なノートを作る人もいますが、きれいなまとめノートを作ることが目的になってしまっている人が、少なくありません。
まとめノートをきれいに作ってそれを使わない人も多い印象です。
おそらく、きれいなまとめノートを作った段階で満足してしまっているのでしょう。
これではただの自己満足で終わってしまいます。
試験勉強の目的は、あくまで試験に受かることで、まとめノート作りはその手段のはずなのに、いつの間にかまとめノート作りが目的となってしまています。
目的と手段を取り違えてはいけません‼
時間をかけてまとめノートを作っても、それを活用しないのであればまさに時間の無駄です。
費用対効果が低いどころか、ゼロです。
もっとも私はまとめノートを作ること自体が無駄だと考えています。
その理由は次に述べます。
現在のテキストはすでにまとめられているので、さらにまとめる必要はない
私が受験した頃は、ほとんどが条文とその解説の羅列という感じでしたから、まとめノートを作る意味もあったのかもしれません。
しかし、現在の市販のテキストを読んでみると図やイラストもたくさん使ってあってよくまとまっています。
すでにまとまっているものをさらにまとめるのは、屋上屋を架すことになります。
さらに、テキストがまとまっているということは、過去問などから出題範囲の絞り込みがされているということです。
これはどういうことかというと、出題範囲全てがテキストに載っているわけではない、つまり、穴があるということです。
このテキストをさらにまとめるのですから、その穴はさらに広がっていきます。
情報はテキスト1冊にまとめるべき
勉強が進んでいくと、試験に関する知識や情報はテキスト、過去問、模試の解説などあちこちに散らばることになります。
これをそのままにしておくと、後でその情報を見たいと思ったときにどこにあるのか分からなくなってしまう可能性があります。
これらの情報をテキスト1冊に集約しましょう。
テキスト一冊に過去問や模試の解説をまとめていくのです。
テキストを母艦として、テキストを見ればすべての情報や参照先がわかるようにするのです。
テキスト1冊に情報をまとめることを、私は「テキストを育てる」と呼んでいます。
テキスト一冊に必要なことをすべてまとめておけば、自宅以外で勉強するときも持っていく荷物が少なくてすみます。
これは試験場に持っていく場合も同じです。
私は、東京法経学院の『行政書士合格ノート―行政書士試験短期合格のためのテキスト』を使っていました。
法令と一般知識が一冊にまとまっていてなかなか使い勝手がよかった記憶がありますが、現在は絶版です。
以下で「テキストを育てる」とはどういうことか詳しく説明します。
テキストを育てるためにする3つのこと
まず、「テキストを育てる」ためにすることは以下の3つです。
・重要な箇所にアンダーラインを引くこと
・ポストイットなどで過去問解説などをまとめてテキストに貼り付けること
・過去問の問題番号をテキストの該当箇所に書き込むこと
重要な箇所にアンダーラインを引く
誰でもやっていることだと思いますが、私のやり方では使う筆記具は赤ボールペンだけです。
これはかつての代ゼミの地理講師、武井正明師に教わった方法です。
複数の色を使うと、持ち替えや切り替えをしなければならず、そこで思考が止まってしまいます。
その点、1色だけならいちいち持ち替えや切り替えの必要もないので集中力も切れにくいです。
「1色じゃ、とても足りないよ!」と思うかもしれませんが、線の種類を変えれば十分です!
「一本線」「二重線」「点線」「囲み」とこれくらい使えば十分です。
私の使い分けは、覚えたい文に引くときは「一本線」、「一本線」を引いた文の中でさらに重要そうな部分は「二重線」、覚えるまでではないが重要そうな部分は「点線」、覚えたい単語は「囲み」といった感じです。
多分に感覚的なところがあるので、各自でやりやすいようにアレンジしてください。
ちなみにおススメの赤ペンは「フリクションノックの赤(0.7)」です。
ポストイットなどで過去問解説などをまとめてテキストに貼り付ける
過去問の解説を読んでいてテキストに書いていない情報があれば、余白などに書き込みます。
余白で足りなければポストイットを使ったり、コピー用紙やメモ用紙を切って「張って剥がせるのり」でテキストに貼り付けます。
とくに、民法の権利関係は絵を描くことが学習の基本となるので、かなり貼り付けた気がします。
ポストイットは少し大きめのものが、メモ用紙はロディアのナンバー16の白かニーモシネのA7がおすすめです。
張って剥がせるのりはドットライナーの黄色がおすすめです。
過去問の問題番号をテキストの該当箇所に書き込む
これは後程、別記事で紹介するつもりなので、ここでは簡単に説明します。
過去問を解いたとき、テキストの該当箇所にその問題番号を書いておきます。
例えば、令和4年12問だとしたら、「R4⑫」という感じです。
これをおこなうメリットは、テキストを読んだとき試験に出るところがわかるので、テキストを読んでいく際にメリハリがつけられることです。
まとめ
以上のように、私は「まとめノート(サブノート)」は作る必要はないと考えています。
それよりもノートをまとめるより、一問でも多くの過去問を解き、一ページでも多く参考書を読み込みましょう。
ただ勘違いしてほしくないのは「参考書をまとめ直したノートを作る必要はない」と言っているのであって、当然授業のノートを取ることを否定しません。
私も予備校や大学の授業のノートはきちんととりました。
ただノートを取ることに夢中になって肝心な授業を聞いていないのでは本末転倒です。
チョットずるいのですが、一番いいのは授業中は先生の話をしっかり聞き、授業の後に友人からノートを借りてコピーすることです。
試験は要領という側面もありますから、この辺りうまく立ち回ってください(笑)。
ブログ村に参加しています。
応援していただけると励みになります。
↓↓↓↓

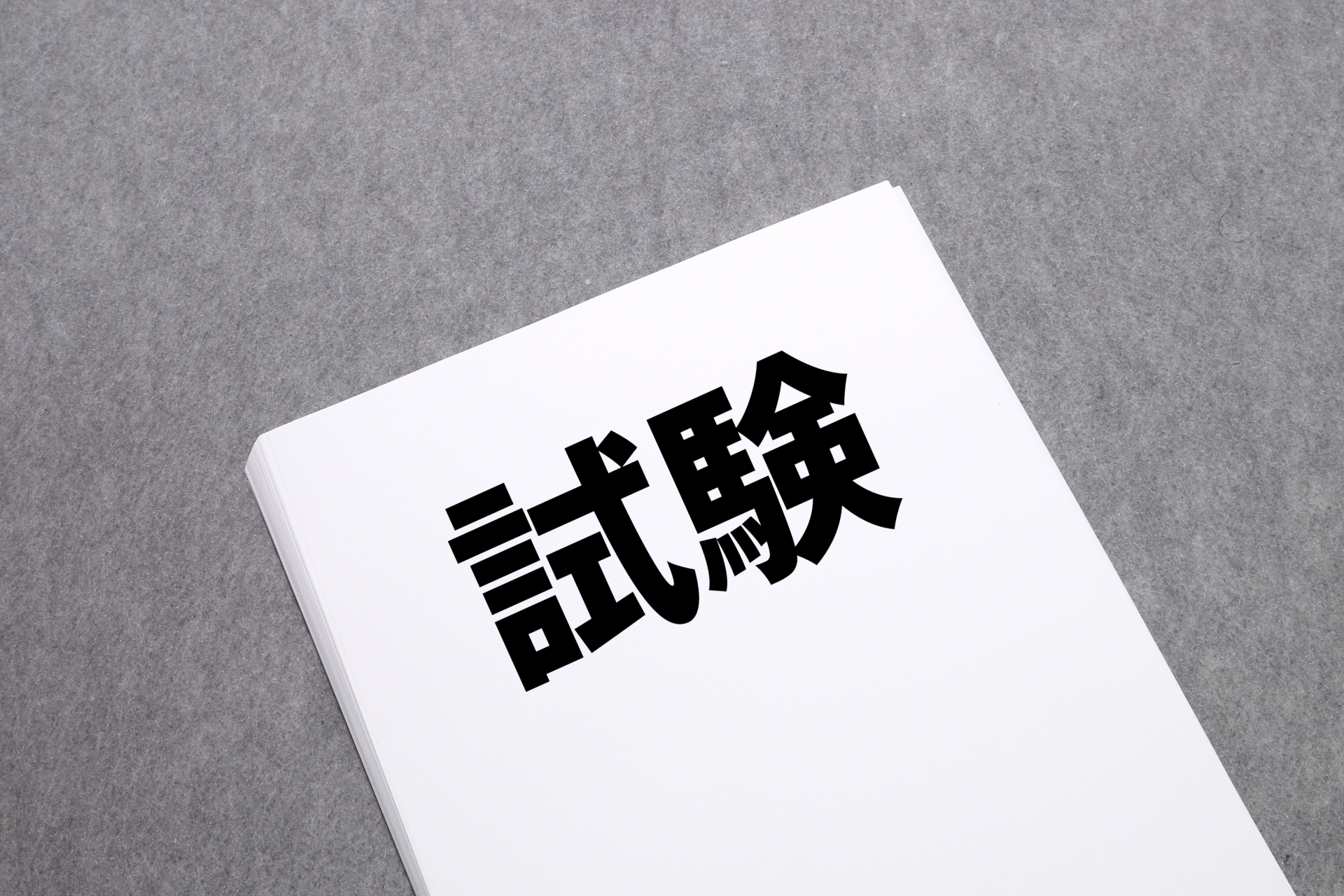
コメント